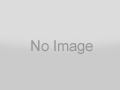
もちろん小松菜育ちのマナツ
鳥専門系の動物病院で受診された文鳥の飼い主さんは、そこの獣医さんに「青菜は与えないで下さい」と言われ、その理由として、「アブラナ科の野菜は甲状腺異常を起こす」との説明を受け、さらに、必要なビタミンは青菜でなく、ビタミンのサプリメント摂るべきで、「食べる喜びを与える」ためなら、レタスを与えるように、アドバイスされたそうだ。
私、文鳥飼育歴長い。今の文鳥たちの初代から数えても17年ほどで(その前も家には文鳥がずっといる)、奇跡的に14代続いている。現在、親子孫曾孫曾曾孫玄孫・・・20数羽飼育しており、毎朝アブラナ科の野菜である小松菜を菜さしに詰めて与え、昨今の天候不順による小松菜価格の高騰に心痛している。・・・つまり、その獣医さんの言説には、「喧嘩売ってるのか!」とならざるを得ない。
獣医さんの中には、昔から、診療室という密室では、かなり珍妙な自説を患者の飼い主に押し付けてしまうケースがあるので、無批判に真に受けないで欲しいと願う。そこで、勝手に喧嘩を買い、批判させてもらう。
1、ゴイトロゲンという物質は、甲状腺にヨウ素が取り込まれるのを阻害する性質があるため、摂取しすぎると甲状腺のヨウ素が欠乏し甲状腺腫などの障害を起こす。
2、ゴイトロゲンを比較的に多く含む食品の一つに、アブラナ科の植物が挙げられる。
3、小鳥の飼料として多く用いられる小松菜もアブラナ科の植物だ。
なるほど、これらの事実だけを念頭に置くなら、その獣医さんの説に行き着くかもしれない。しかし、それは、あまりに現実を無視し、科学的な根拠の無い、粗雑な結論ではあるまいか。
そもそも、アブラナ科の食品に含まれるのは、ゴイトロゲンそのものではなく、それに変質するグルコシノレートという物質のようだが、その含有量は同じアブラナ科でもいろいろで、ひとくくりにするのは乱暴だ。また、その影響も生物種によって全く異なるはずであり、実験的裏付けもないままに、個別の生物種の飼育に危険性を指摘すれば、まるで科学的論拠(エビデンス)を持たない浮説となってしまう。
その獣医さんにどれほど飼育の経験があるのか知らないし、文鳥なら何百年と飼育されている過去について、どの程度理解しているのか知る由もないが、経験で良ければありふれている。例えば、毎日我が家で小松菜を食べている文鳥たちに甲状腺障害は存在しない。もちろん、とんかつ屋でいつもキャベツの千切りを、どんぶりいっぱい食べる人がいても、別に問題にはなっていないし、アブラナ科の野菜を毒物と見なして食べない人は、極めつけに珍しい。つまり、ごく微量しか含まれず、同じアブラナ科でも桁違いに含有するとされる芽キャベツを、毎日好んで食べ続けでもしない限り(そんな人は有り得ないと思うが・・・)、問題にならない程度の危険性でしかないのである。
例えば、春の七草のうち3つはアブラナ科の植物であるように(ナズナ・スズナ・スズシロ)、アブラナ科の植物は野草としてもあふれており、当然ながら野生動物の食用になっている。もちろん、人間の食品としても小鳥の飼料としても、何百年と使用されている大根や小松菜といった栽培野菜も、アブラナ科である。普通に食べて毒性があるなら、とっくの昔に経験上食用外とされたか、哀れにもそれを食べる生き物は絶滅したか、さっさと毒に耐性を身に付けなければならない。つまり、大して毒がないどころか、利点の方が大きいので、食用となっていると考えるのが自然、というより一般常識と言って良いかと思う。
一般常識よりも栄養学的な小理屈が好きな人は、否定的要素ばかりではなく、肯定的要素にも注目してもらいたい。このグルコシノレートという一種の辛味成分こそが、解毒効果があるとされているものであり、近年では抗癌作用が期待されてもいるのである。ご存知であろうか?(もちろん、私も良くは知らない。健康食品に興味ないので)ご存知なら、否定的なことにばかり飛びつく、その自分の心理は、科学的な合理性に基づくものではなく、たんに情緒的な思い込みに過ぎないのではないかと、少し疑ったほうが良いだろう。
偏頗な知識で、昔から食べられていて、今も普通の飼い主が普通に食べさせているものを否定するような態度は、まったく感心できない。どうしても、その説を広めたければ、科学的な実証をもとにして主張し、多くの人の検証を待つべきで、密室の中で、反論できない立場の人間に対して自分だけが信じている奇説を唱えるなど、破廉恥で卑怯な態度でしかないと、私は強く抗議したい。
正々堂々と裏付けを求めるなら、ゴイトロゲンを小鳥の大まかな品種別に、どの程度与えたら影響が出るかの実験と、どの植物がどの程度ゴイトロゲンの前駆体を持ち、どの程度変質するのか明らかにしなければなるまい。この点、人間の方は、大体はわかっていて、甲状腺を阻害することもアブラナ科に比較的多く含まれることもわかった上で、大量に食べなければ何の問題もないこともわかっているから、実際みんな食べている。鳥に対する影響の実験データは寡聞にして知らないが、なぜ、人間では問題ないとされる微量を含むことを、針小棒大に問題視するのであろうか。これは不可思議と言うしかない。人間のデータに拠りながら、結論を違えるエビデンスをお訊きしたいものである。
以下補足
事実は、
1、ゴイトロゲンという物質は、甲状腺にヨウ素が取り込まれるのを阻害する性質があるため、≪摂取しすぎると≫甲状腺のヨウ素が欠乏し甲状腺腫などの障害を起こす。
2、食用とされているアブラナ科の植物にも、ゴイトロゲンに変質する物質が含まれているが、その量は≪わずかで問題とされない≫。
だけのことである。これに対しこの獣医さんの主張は、「1だから、きっと鳥さんにも悪い影響があるはずで、食べさせちゃダメ!」、と言っているのと同じであろう。≪摂取しすぎると≫問題だが、≪わずかで問題とされない≫から、人間は≪普通に食用とし続けている≫が、鳥には禁止としなければならないなら、その理由を詳らかにしてもらいたい。
鳥類の中には、ゴイトロゲンに過剰反応する種類がないとは言えないが、少なくとも、湿潤気候において、アブラナ科の植物も食性に含めて進化した文鳥のような生き物が、「アブラナ科の野菜は甲状腺異常を起こす」としたら、それは生命進化の奇跡と言うしかない。それが、適応進化の合理性において、有り得ないことくらい、いかに合理的で論理的な思考性に乏しい幼児であっても、理解できないはずはないと思うのだが、如何であろうか。
この獣医さんは、診療室内で、ヨウ素不足にならないようにイソジンのうがい薬を勧めたり、市販のアワ玉やボレー粉をばい菌の巣窟のように主張したりしていたと、昔から仄聞している(【参照】)。その無茶な思い込みの数々の基礎は、日本の飼鳥に甲状腺障害が多いという、やはり思い込みにあると私は見なしているが、確かに、周囲を海洋に囲まれ、土壌というより雨水にヨウ素を含むため、ヨウ素の過剰(昆布などの食べ過ぎ)はあっても不足は起きにくい風土にありながら、その露地で育った生鮮野菜を与えず、ヨウ素を多く含むボレー粉も与えず、ヨウ素の給源は飲水に求めるだけといった特異な飼育を行えば、ヨウ素不足に陥る危険は高まるのは、火を見るより明らかであろう。
この獣医さんやその他の先達の活躍もあって、小鳥を診療する獣医さんも増えてきているようで、競争も激化してきたのだろうか、一昔前のように、診療室でわめいたり怒鳴ったり威張り散らしたりする、権柄症状を呈する獣医さんの話は聞かなくなってきている。しかし、診療室内で、個別種の飼育に関しての知見などたかが知れていることも自覚せず、偏頗な知識だけの机上の空論以外の何ものでもない科学的合理性も怪しい独自の飼育法を、上から『指導』するのは(アドバイスのつもりでも、初心者は絶対的に正しい飼育方法の指導と受け取る。実際は、獣医さんによって言うことはバラバラだが、その事実は初心者は知らない)、有害なのでやめていただきたい。どうしても行いたければ、公開して世に問うなり(昔、セキセイインコの不思議な飼育本を書いた鳥専門獣医さんがいた【参照】)、少なくとも、仲間内の獣医さんたちとの間くらいでは、コンセンサスを得た上でお願いしたいものである。臨床医の研究会は臨床技術を磨くもので、他のことはまったく無用だと思うが、飼育指導などと称し、個々で違った意見、それも常識はずれの奇抜なものを振り回されては、飼い主ははなはだしく迷惑し、余計なことに思い煩うことになってしまう。もちろん、青菜を取り上げられた鳥の健康も心配される。
治療の一環として、基礎を逸脱した常識外の飼育指導を行いたいのなら、せめて臨床医の研究会名で一定の統一見解なりガイドラインをお作りにならないと、かえって信用を落とす結果になると思う。密室での無駄口、軽はずみな理屈を自重されるか、より積極的に密室の外での議論を深めていただきたい。

コメント